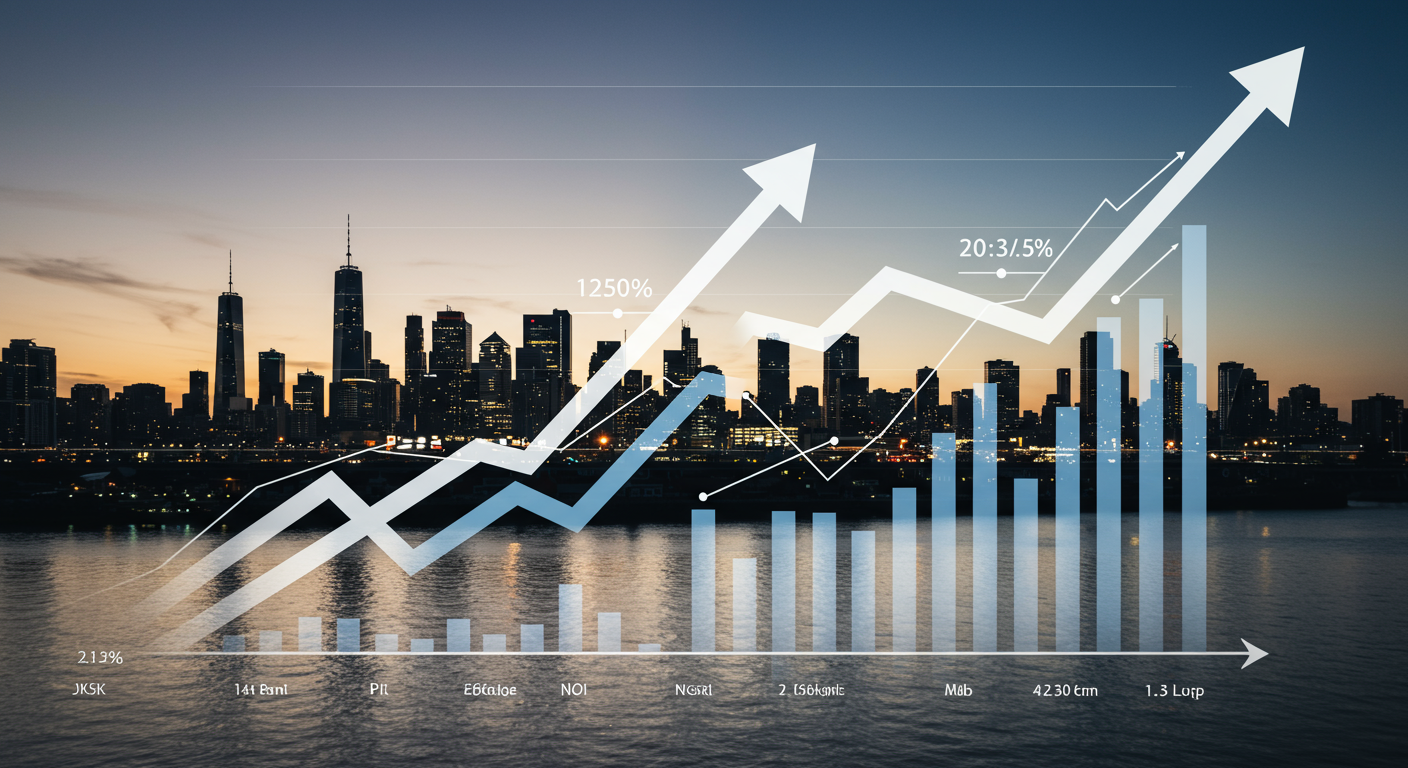「会社の経営状況を分析して」と上司に言われたけれど、ROAやROEなど似た指標が多くて、どれを使えばいいか迷っていませんか。「総資本営業利益率を計算してみたものの、この数字が良いのか悪いのか判断できない」「ROAとの違いが結局よくわからない」といった悩みを抱えている方は少なくありません。
こうした悩みが生まれるのは、財務指標について体系的に学ぶ機会が少ないからです。特に総資本営業利益率や総資産営業利益率のように名前が似ている指標は混同しやすく、自己流で分析を進めた結果、指標の持つ本当の意味を捉えきれず、的確な打ち手が見えなくなってしまうことがよくあります。
この記事では、総資本営業利益率の基本的な意味からROAとの明確な違い、実務ですぐに使える計算方法、そして具体的な改善策まで、会社の成長を後押しする知識を網羅的に解説します。
- 総資本営業利益率は「会社全体の資本を使って、本業でどれだけ効率よく稼げたか」を示す収益性の指標です。
- 計算式は「営業利益 ÷ 総資本 × 100」。ROAとの大きな違いは、本業の儲けである「営業利益」を使う点にあります。
- まずは業界平均と比較しましょう。全産業の一般的な目安は5%以上ですが、自社が属する業界の数値を参考にすることが重要です。
- 改善するには、「利益率を上げる(コスト削減など)」か「資本効率を上げる(不要資産の売却など)」の2つの視点から具体的なアクションを考えましょう。
営業専用のAI議事録・商談解析ツールSTRIX

【解決できる課題】
- 営業メンバーがSFA/CRMに情報入力しないため、社内に定性情報が残らない
- 営業メンバーの報告内容が正確でなく、個別の状況確認や録画視聴に時間がかかってしまう
- 営業戦略策定に必要な情報が溜まっておらず、受注/失注分析ができない・有効な示唆がでない
- 今注力すべき案件の優先度が立てられず、営業活動が非効率
- フォローアップすべき案件が漏れてしまい、機会損失が生まれている
- 提案や新人教育が属人化しており、事業拡大のボトルネックになっている
総資本営業利益率とは?会社の「本当の稼ぐ力」を測る指標
総資本営業利益率とは、一言でいうと「会社が事業のために集めたお金(総資本)を使って、本業でどれだけ効率よく利益(営業利益)を稼げたか」を示す指標です。
会社の健康診断に例えるなら、身長や体重といった個別の数値だけでなく、それらを総合的に評価して「健康状態は良好か」を判断するようなもの。この数値が高いほど、資本を効率的に使って本業でしっかり稼げている「筋肉質な経営」ができていると評価できます。
この指標は、以下の2つの要素から成り立っています。
- 総資本:会社が事業を行うために調達した資金の合計。返済が必要な借入金(負債)と、株主からの出資金など返済不要な自己資本(純資産)を合わせたものです。貸借対照表(B/S)の右側に記載されている「負債・純資産の合計」に相当します。
- 営業利益:会社の本業から生み出された利益のこと。売上高から売上原価、さらに販売費及び一般管理費(人件費や広告費など)を差し引いて計算されます。損益計算書(P/L)で確認できます。
つまり、総資本営業利益率は、経営の効率性を測るための非常に重要なものさしなのです。
なぜ重要?総資産利益率(ROA)との決定的な違いを理解する
総資本営業利益率を理解する上で、多くの人がつまずくのが「総資産利益率(ROA)」との違いです。この2つは名前も似ており混同しがちですが、見ているものが根本的に異なります。この違いを理解することが、的確な経営分析への第一歩です。
1. 総資産利益率(ROA)との違いは「利益」の種類
総資本営業利益率とROA(Return On Assets)の最も大きな違いは、計算に使う「利益」の種類です。
- 総資本営業利益率:分子に「営業利益」を使う → 本業の収益力を見る指標
- ROA(総資産利益率):分子に「当期純利益」を使う → 最終的な会社の収益力を見る指標
「営業利益」は本業で稼いだ利益ですが、「当期純利益」はそこから営業外の損益(受取利息や支払利息など)や、その期だけの特別な損益(固定資産の売却益や災害損失など)を加味した、会社に残る最終的な利益です。
例えば、本業は非常に好調で営業利益がたくさん出ていても、保有していた土地の売却で大きな損失が出た場合、当期純利益は少なくなり、ROAは低くなります。逆に、本業が不調でも、資産売却で一時的に大きな利益が出ればROAは高く見えてしまいます。
このように、ROAは一時的な要因に左右されやすい側面があります。一方で、総資本営業利益率は、そうしたノイズを除いた「会社の事業そのものが持つ、継続的な稼ぐ力」を正確に評価するのに適しているのです。
2. 「総資産営業利益率」や「経営資本営業利益率」との関係
実務では、「総資産営業利益率」や「経営資本営業利益率」といった言葉も使われ、混乱の原因になります。これらの関係を整理しておきましょう。
まず、会計のルール上、会社の貸借対照表では「資産の合計」と「負債と純資産の合計(=総資本)」は必ず一致します。そのため、単純に計算する上では「総資産」と「総資本」は同じ金額になり、「総資産営業利益率」と「総資本営業利益率」は同じ指標として扱われることが多くあります。
しかし、より厳密な財務分析では、分母となる資本を「事業に投下された資本」と捉え、買掛金や未払金といった事業活動の中で自然に発生する負債(支払利息のかからない負債)を除いて考える場合があります。その際に使われるのが「経営資本営業利益率」です。これは、よりシビアに「利益を生むために能動的に調達・投下した資本(有利子負債+自己資本)に対する効率」を見ています。
どの指標を使うかは分析の目的によりますが、まずは「総資本営業利益率=本業の効率性を見る基本指標」と覚えておけば問題ありません。
総資本営業利益率の計算式と求め方【財務諸表のここを見る】
総資本営業利益率の求め方はシンプルです。ここでは、具体的な計算式と、計算する際に間違いやすい注意点について解説します。
1. 計算式は「営業利益 ÷ 総資本」
総資本営業利益率は、以下の計算式で求められます。
総資本営業利益率(%) = 営業利益 ÷ 総資本 × 100
計算に必要な数字は、会社の決算書である「損益計算書(P/L)」と「貸借対照表(B/S)」から見つけます。
- 営業利益:損益計算書(P/L)に記載されています。
- 総資本:貸借対照表(B/S)の「負債合計」と「純資産合計」を足した金額です。「資産合計」と同じ金額になります。
例えば、営業利益が5,000万円、総資本が5億円の会社の場合、総資本営業利益率は「5,000万円 ÷ 5億円 × 100 = 10%」となります。
2. 計算でよくある間違いと注意点
計算式は簡単ですが、より正確に分析するためには注意点が一つあります。それは、分母の「総資本」に期首と期末の平均値を使うことです。
なぜなら、分子の「営業利益」は1年間という期間の活動成果(フロー)であるのに対し、分母の「総資本」は期末時点など一時点での残高(ストック)だからです。期間と時点という異なる性質のものをそのまま計算すると、実態からズレが生じる可能性があります。
そこで、期間中の平均的な資本額で計算するために、期首と期末の総資本を足して2で割った「期中平均総資本」を使うのが一般的です。
正確な計算式:営業利益 ÷{ (期首総資本 + 期末総資本) ÷ 2 }× 100
この方法を使うことで、期間中の増資や大規模な設備投資などによる資本の変動をならし、より精度の高い分析が可能になります。
前述の通り、貸借対照表の「総資産」と「総資本」は同額のため、実務上は「営業利益 ÷ 総資産」で計算されることも多くあります。これを「総資産営業利益率」と呼びます。
一方で、より厳密な分析では、分母を「投下資本」と考えることがあります。これは、株主から集めた「自己資本」と、銀行などから借り入れた「有利子負債」の合計額です。買掛金や未払金のように、事業活動から自然に発生し、利息を生まない負債は除外します。
なぜなら、「株主や金融機関がリスクを取って会社に投じた資本に対し、どれだけのリターンを生んだか」という、よりシビアな資本効率を測れるからです。自社の分析を行う際は、どの範囲の資本で計算するのかを明確にすることが重要です。
総資本営業利益率の目安はどれくらい?業界別の平均値も紹介
自社の総資本営業利益率を計算できたら、次に気になるのは「その数値が良いのか悪いのか」という点でしょう。ここでは、一般的な目安と、より実態に即した評価を行うための業界平均について解説します。
まず、全産業における一般的な目安として「5%」が一つの基準とされています。経済産業省や中小企業庁の統計調査を見ても、全産業の平均値は概ね5%前後で推移していることが多いです。もし自社の数値が5%を上回っていれば、資本効率は平均以上と考えることができます。
ただし、この「5%」という数字はあくまで全体平均であり、絶対的なものではありません。総資本営業利益率は、業種によって大きく異なるからです。
例えば、大規模な工場や設備が必要な製造業では、多くの資本が必要になるため総資本営業利益率は低めになる傾向があります。一方で、大きな設備投資が不要なサービス業やIT産業では、少ない資本で高い利益を上げやすいため、数値は高くなる傾向にあります。
そのため、自社の数値を評価する際は、全体平均だけでなく、自社が属する業界の平均値と比較することが非常に重要です。業界平均は、政府が公表している信頼性の高い統計データで確認できます。
代表的なものとして、財務省の「法人企業統計調査」があります。例えば、令和4年度の調査結果から、いくつかの業種の平均値を見てみましょう。
| 業種 | 総資本営業利益率(ROA)の平均 |
|---|---|
| 製造業 | 6.2% |
| 情報通信業 | 8.6% |
| 卸売業 | 5.3% |
| 小売業 | 3.9% |
| サービス業 | 7.0% |
※出典:財務省「法人企業統計調査」(令和4年度)のデータ(売上高営業利益率×総資本回転率)を基に算出
このように、自社の立ち位置を客観的に把握するためには、信頼できる公的データを活用し、同業他社と比較する視点を持つことが不可欠です。
総資本営業利益率を改善するための具体的な3つのアプローチ
分析の結果、自社の総資本営業利益率が業界平均より低い、あるいはもっと高めたいと考えた場合、どうすればよいのでしょうか。この指標は、2つの要素に分解することで、改善の具体的な打ち手が見えてきます。
総資本営業利益率は、以下の式に分解できます。
総資本営業利益率 = 売上高営業利益率 × 総資本回転率
- 売上高営業利益率(営業利益 ÷ 売上高):収益性、つまり「売上からどれだけ効率よく利益を残せているか」を示す。
- 総資本回転率(売上高 ÷ 総資本):効率性、つまり「資本をどれだけ効率よく売上に繋げているか」を示す。
つまり、総資本営業利益率を改善するには、「収益性を高める」か「効率性を上げる」、あるいはその両方が必要になります。
1. 【収益性の改善】売上高営業利益率を高める
収益性を改善するには、分子である「営業利益」を増やす必要があります。アプローチは大きく2つです。
- 売上を増やす
- 商品・サービスの単価を上げる
- 販売数量を増やす(新規顧客獲得、リピート率向上)
- 顧客単価を上げる(クロスセル、アップセル)
- コストを削減する
- 変動費を削減する(仕入先の見直し、製造プロセスの改善)
- 固定費を削減する(家賃や人件費、広告宣伝費などの見直し)
自社の損益計算書を見ながら、どの項目に改善の余地があるかを検討することが重要です。
2. 【効率性の改善】総資本回転率を上げる
効率性を改善するには、少ない資本で多くの売上を上げる必要があります。つまり、分母である「総資本」を圧縮することが基本的なアプローチです。
- 不要な資産を売却・処分する
- 使っていない機械や設備、不動産(遊休資産)を売却する
- 投資効果の低い有価証券などを現金化する
- 売上債権(売掛金・受取手形)を減らす
- 入金サイクルを早める交渉を行う
- 請求から入金までの管理を徹底し、回収漏れを防ぐ
- 棚卸資産(在庫)を減らす
- 需要予測の精度を上げ、過剰在庫を防ぐ
- 在庫管理システムを導入し、滞留在庫を可視化・削減する
貸借対照表の資産の部をチェックし、長期間動いていない資産や、現金化できていない債権がないかを確認することが第一歩です。
大掛かりな設備売却などが難しい中小企業でも、総資本回転率を高めるためにできることはたくさんあります。まずは「在庫」と「売掛金」の管理を見直してみましょう。
- 在庫リストを作成する:すべての在庫をリストアップし、最終出荷日や仕入日を記録します。半年以上動いていない「滞留在庫」があれば、セール販売や処分を検討しましょう。
- 売掛金の年齢調査を行う:請求日からの経過日数ごとに売掛金をリスト化します。回収が遅れている取引先はないか、定期的にチェックする習慣をつけるだけで、回収意識が高まります。
こうした地道な取り組みが、貸借対照表のスリム化に繋がり、資本効率の改善に直結します。
3. 自社の課題はどこか?2つの要素で分析する
改善策を検討する上で最も重要なのは、自社の課題が「収益性(売上高営業利益率)」と「効率性(総資本回転率)」のどちらに、より大きくあるのかを特定することです。
業界平均や競合他社の数値を参考に、分解した2つの指標を比較してみましょう。
- ケースA:売上高営業利益率は高いが、総資本回転率が低い → 稼ぐ力はあるが、資産が多すぎる(過剰在庫、遊休資産など)か、売上への変換が遅い(売掛金回収の遅れなど)可能性があります。資産の圧縮や回転率向上策が有効です。
- ケースB:総資本回転率は高いが、売上高営業利益率が低い → 資産を効率よく売上に繋げているが、利益が薄い可能性があります。コスト削減や、より付加価値の高い商品・サービスへの転換が課題となります。
このように分解して分析することで、闇雲に施策を打つのではなく、自社の弱点に的を絞った効果的な改善アクションプランを立てることができます。
まとめ:総資本営業利益率を正しく理解し、会社の成長に繋げよう
本記事では、総資本営業利益率の基本的な意味から計算方法、ROAとの違い、そして具体的な改善アプローチまでを解説しました。
最後に重要なポイントを振り返ります。
- 総資本営業利益率は、会社が「本業でどれだけ効率よく稼げているか」を示す重要な指標です。
- ROAとの最大の違いは、一時的な損益を含まない「営業利益」を使う点にあり、会社の継続的な実力を測るのに適しています。
- 計算した数値は、業界平均と比較することで自社の客観的な立ち位置を把握できます。
- 改善するには、「収益性(売上高営業利益率)」と「効率性(総資本回転率)」に分解し、自社の課題がどこにあるのかを特定することが重要です。
総資本営業利益率は、ただ数値を計算して終わりにするのではなく、その背景にある経営課題を読み解き、具体的なアクションに繋げることで初めて真価を発揮します。この指標を正しく理解し、自社の成長を加速させるための強力な武器として活用していきましょう。