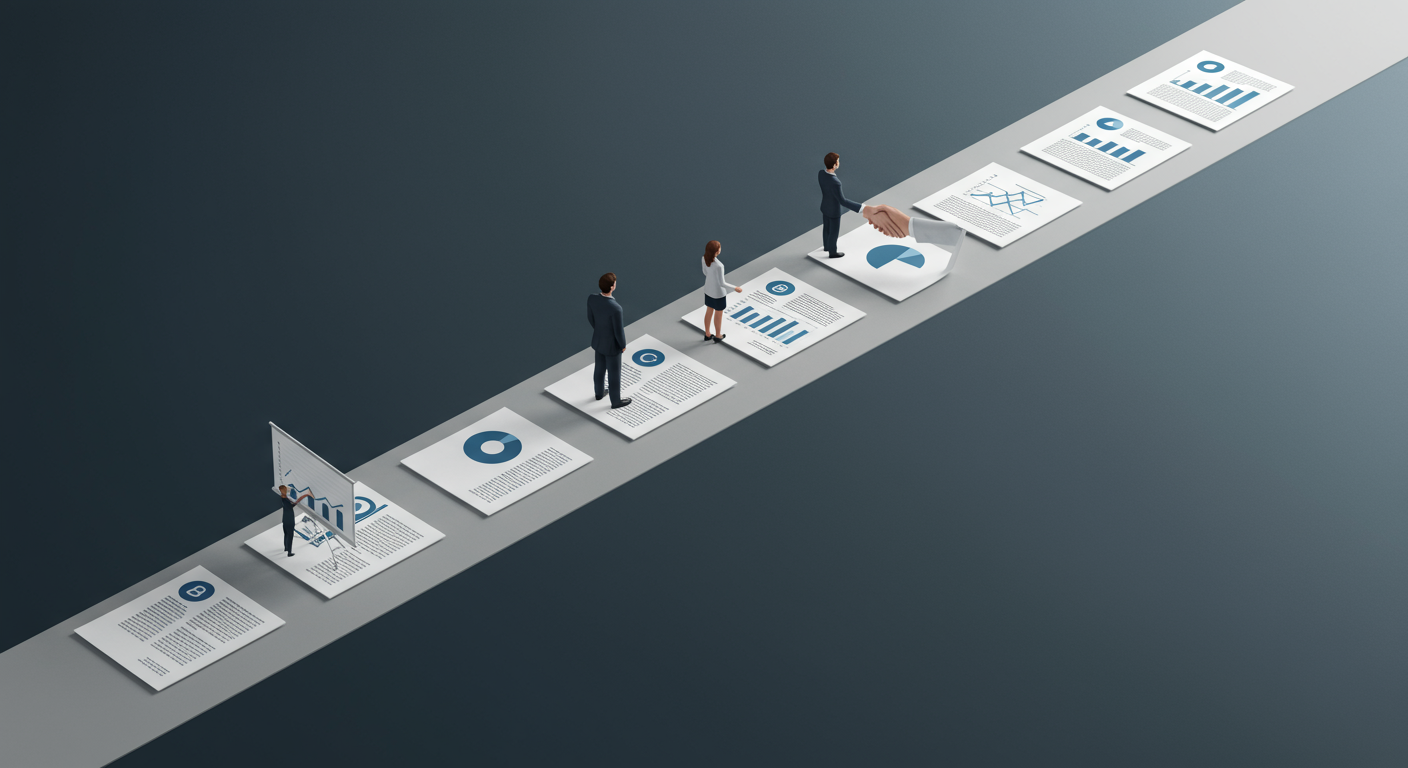思うように受注が取れず、営業提案書の見直しを考えていませんか。「時間をかけて作ったのに手応えがない」「そもそも、何をどの順番で書けば相手に響くのだろうか」といった悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。
営業提案書の作り方を体系的に学ぶ機会は意外と少なく、多くの担当者が自己流で作成しているのが実情です。その結果、自社製品の機能説明に終始してしまったり、情報量が多すぎて要点が伝わらなかったりと、かけた時間と労力が成果に結びつかないケースが後を絶ちません。
受注率を上げる営業提案書の基本構成から、顧客の心を動かす書き方のコツ、そしてチームで品質を標準化する方法まで、成果に直結するポイントを網羅的に解説します。
- 提案書の主役はあなたではなく『顧客』です。常に相手の課題解決を起点に構成しましょう。
- 伝わる提案書は『課題提起 → 解決策 → 導入効果 → 実行計画 → 費用』の黄金構成でできています。
- PREP法(結論→理由→具体例→結論)を意識するだけで、分かりやすさは格段に向上します。
- 品質の高いテンプレートは『考える時間』を削減し、あなたを本来の営業活動に集中させてくれる最強の武器になります。
営業専用のAI議事録・商談解析ツールSTRIX

【解決できる課題】
- 営業メンバーがSFA/CRMに情報入力しないため、社内に定性情報が残らない
- 営業メンバーの報告内容が正確でなく、個別の状況確認や録画視聴に時間がかかってしまう
- 営業戦略策定に必要な情報が溜まっておらず、受注/失注分析ができない・有効な示唆がでない
- 今注力すべき案件の優先度が立てられず、営業活動が非効率
- フォローアップすべき案件が漏れてしまい、機会損失が生まれている
- 提案や新人教育が属人化しており、事業拡大のボトルネックになっている
そもそも営業提案書とは?企画書との違い
営業提案書とは、顧客が抱える課題を解決するために、自社の製品やサービスを提案し、契約(受注)に繋げることを目的とした書類です。
提案書の主役はあくまで「顧客」であり、「顧客の課題をいかに解決できるか」という視点で作成することが最も重要です。
一方で、よく混同されがちな書類に「営業企画書」があります。両者の違いを理解しておくことで、目的がブレない書類作成が可能になります。
| 営業提案書 | 営業企画書 | |
|---|---|---|
| 目的 | 顧客からの受注獲得 | 社内での承認獲得 |
| 提出先 | 顧客(社外) | 上司や経営層(社内) |
| 内容の中心 | 顧客の課題解決策 | 自社の戦略・目標達成プラン |
簡単に言えば、営業提案書は「顧客のための書類」、営業企画書は「自社(社内)のための書類」と覚えておくと良いでしょう。この記事では、顧客に提出する「営業提案書」の作り方に焦点を当てて解説します。
受注率が上がる営業提案書の基本構成【テンプレート付き】
説得力のある営業提案書には、情報を伝えるための「型」が存在します。公的機関や多くの企業で推奨されているのが、以下の6つの要素で構成される基本的なフレームワークです。
この流れに沿って作成することで、顧客は課題から解決策、そして導入後の未来までをスムーズに理解できます。
- 1. 表紙・タイトル
- 2. 課題提起(現状の課題と理想の姿)
- 3. 解決策の提示
- 4. 導入効果と根拠(導入事例・データ)
- 5. 実行計画(スケジュール・体制)
- 6. 費用・お見積もり
もちろん、これはあくまで基本の型です。提案先の状況や商材に応じて、順番を入れ替えたり、要素を追加したりと柔軟に対応することが成功の鍵となります。
(※ここにテンプレートのダウンロードリンクが設置されます)
1. 表紙・タイトル
表紙は提案書の「顔」です。誰に向けた、何の提案なのかが一目で分かるように、以下の情報を簡潔に記載しましょう。
- 宛先:会社名、部署名、担当者名
- 提案タイトル:「〇〇で実現する業務効率化のご提案」など、導入メリットが伝わるタイトル
- 提案日:提出する日付
- 自社情報:会社名、部署名、担当者名、連絡先
2. 課題提起(現状の課題と理想の姿)
提案の導入部分であり、最も重要なパートです。ここでは、事前のヒアリングで得た情報をもとに、顧客が認識している課題(顕在ニーズ)と、まだ気づいていない可能性のある課題(潜在ニーズ)を言語化します。
「貴社は現在〇〇という課題をお持ちです」と事実を述べるだけでなく、「この課題を解決することで、〇〇という理想の姿を実現できます」と、ポジティブな未来像を提示することがポイントです。「この会社は、私たちのことを深く理解してくれている」と顧客に感じてもらうことを目指しましょう。
3. 解決策の提示
前のパートで提示した課題に対し、「なぜ自社の製品・サービスがその解決に最適なのか」を具体的に示します。
ここで注意したいのは、単なる機能の羅列にならないことです。「この機能を使えば、〇〇という課題をこのように解決できます」というように、必ず課題と結びつけて説明しましょう。顧客が知りたいのは機能のスペックではなく、「その機能が自分たちの問題をどう解決してくれるのか」です。
4. 導入効果と根拠(導入事例・データ)
解決策を導入することで、具体的にどのようなメリット(効果)が得られるのかを提示します。説得力を持たせるために、できるだけ具体的な数字やデータを用いて説明しましょう。
- 定量的効果:「コストを〇〇%削減」「作業時間を月〇〇時間短縮」など、数値で示せる効果
- 定性的効果:「従業員のモチベーション向上」「顧客満足度の向上」など、数値化しにくい効果
また、「同様の課題を抱えていた〇〇社では、導入後〇ヶ月で〜という成果が出ました」といった導入事例を示すことで、提案の信頼性が飛躍的に高まります。
5. 実行計画(スケジュール・体制)
顧客が導入を決めた後、どのようなステップで進んでいくのかを具体的に示し、不安を解消するパートです。契約から導入、運用開始までの大まかなスケジュールや、導入をサポートする体制(担当者、サポート窓口など)を明記します。
これにより、顧客は導入後の具体的なイメージを持つことができ、「これなら安心して任せられそうだ」と感じるでしょう。
6. 費用・お見積もり
最後に、提案内容にかかる費用を提示します。複数のプランがある場合は、それぞれのプランで提供される内容と価格を分かりやすく表形式で示すのがおすすめです。
単に金額を提示するだけでなく、「〇〇という効果に対して、月々の投資は〇円です」というように、これまでのパートで説明した導入効果と結びつけ、費用対効果の高さを伝える工夫が重要です。
顧客の心を動かす!営業提案書を作成するための5つの重要ポイント
基本構成という「骨格」を理解したら、次はその質を高める「肉付け」の作業です。構成通りに書くだけでは、ありきたりな提案書になってしまいます。他社と差をつけ、顧客の心を動かすために、以下の5つのポイントを意識しましょう。
1. 徹底した「相手目線」で課題の解像度を上げる
良い提案書の主語は、常に「顧客」です。「私たちが提供できること」ではなく、「貴社が実現できること」という視点で全体を構成しましょう。
そのためには、提案書を作成する前のヒアリングが極めて重要になります。顧客のビジネスモデル、業界の動向、担当者のミッションなどを深く理解し、「なぜ今、この提案が必要なのか」という問いに対して、顧客以上に深く考え抜く姿勢が、提案の説得力を生み出します。
2. PREP法で「分かりやすさ」を極める
PREP法とは、Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(結論)の順で話を構成するフレームワークです。グロービス経営大学院のようなビジネススクールでも推奨されるこの手法は、分かりやすく説得力のあるコミュニケーションに非常に有効です。
提案書の各スライドやセクションをこのPREP法に沿って構成するだけで、論理的で理解しやすい流れを作ることができます。まず結論を伝え、読み手の関心を引きつけた上で、理由と具体例で納得感を高めましょう。
3. 数字とデータで「説得力」を裏付ける
「コストを大幅に削減できます」という曖昧な表現よりも、「導入企業の平均実績として、年間コストを15%削減できます」と具体的な数字で示した方が、はるかに説得力が増します。
自社の実績データ、公的機関の調査データ、市場データなど、客観的な事実に基づいて主張を裏付けることで、提案全体の信頼性が向上します。グラフや図を効果的に使い、視覚的に分かりやすく見せる工夫も重要です。
4. ストーリーで感情に訴えかける
人は論理だけで動くわけではありません。特に最終的な意思決定においては、感情が大きな役割を果たします。単なる情報の羅列ではなく、顧客が「自分ごと」として捉えられるストーリーを意識しましょう。
例えば、「現状の課題(悪役)によって、現場の皆さんは疲弊しています。しかし、私たちのソリューション(ヒーロー)を導入することで、皆が笑顔で働ける理想の職場(ハッピーエンド)が実現します」といった物語を描くことで、顧客の感情に訴えかけ、導入への意欲を掻き立てることができます。
5. デザインは「見やすさ」を最優先する
どれだけ内容が素晴らしくても、読みにくいデザインではその価値は伝わりません。プロのデザイナーである必要はありませんが、「見やすさ」を最優先したデザインの基本は押さえておきましょう。
- フォント:読みやすいゴシック体を基本とし、サイズは12pt以上を目安にする。
- 配色:使う色は3〜4色に絞り、統一感を出す。特に強調したい部分以外は落ち着いた色を選ぶ。
- 余白:スライド全体に余白を十分に取ることで、圧迫感がなくなり、洗練された印象になる。
- 図やイラスト:文字ばかりでなく、図やイラスト、アイコンなどを適度に使い、視覚的な理解を助ける。
過度な装飾は避け、シンプルで分かりやすいデザインを心がけることが重要です。
自社製品の魅力を顧客視点で整理する際に役立つフレームワークが「FABE(ファブ)分析」です。
- Feature(特徴):製品・サービスの客観的な特徴や仕様。
- Advantage(優位性):競合他社と比較した際の強みや優れている点。
- Benefit(顧客便益):顧客がその製品・サービスから得られる具体的な利益や価値。
- Evidence(証拠):便益を裏付ける客観的なデータや導入事例。
多くの提案書は「F(特徴)」や「A(優位性)」の説明に終始しがちです。しかし、顧客が最も知りたいのは「B(便益)」です。このフレームワークを使って情報を整理することで、顧客の心に響く提案内容を組み立てることができます。
やってはいけない!よくある営業提案書の失敗例と改善策
ここでは、多くの営業担当者が陥りがちな失敗例を3つ挙げ、それぞれの改善策を解説します。自身の提案書が当てはまっていないか、チェックしてみましょう。
失敗例1:自社製品の説明に終始している
最もよくある失敗が、顧客の課題そっちのけで、自社製品の機能やスペックを延々と説明してしまうケースです。これは「提案」ではなく、単なる「製品紹介」に過ぎません。
【改善策】
常に「顧客の課題」を主語にして語りましょう。「この機能は〇〇という課題を解決するためにあります」というように、すべての説明を顧客のメリットに結びつけることが重要です。前述の「FABE分析」を活用し、顧客にとっての価値(Benefit)を明確に伝える意識を持ちましょう。
失敗例2:情報量が多すぎて要点が分からない
伝えたいことが多いあまり、1枚のスライドに文字や図を詰め込みすぎてしまうケースです。情報量が多すぎると、読み手は何が重要なのかを理解できず、読む気力さえ失ってしまいます。
【改善策】
「1スライド=1メッセージ」の原則を徹底しましょう。1枚のスライドで伝えたいことを1つに絞り、そのメッセージを補強するための情報だけを記載します。詳細なデータや補足情報は、口頭で説明するか、 appendix(補足資料)として巻末にまとめるのがスマートです。
失敗例3:誰にでも当てはまる一般論しか書かれていない
忙しいからといって、過去の提案書を使い回し、宛名だけを変えて提出していませんか。顧客は「これはうちの会社のために作られた提案書ではないな」とすぐに見抜きます。
【改善策】
提案書は必ず顧客ごとにカスタマイズしましょう。ヒアリングで得た顧客独自の言葉や課題、業界特有の事情などを盛り込むことで、「自分たちのために真剣に考えてくれた」という熱意が伝わります。テンプレートを活用しつつも、必ず「その顧客だけ」の要素を加えることが、信頼関係を築く第一歩です。
【管理職向け】チームで提案書の品質を標準化する方法
個人のスキルアップだけでなく、組織としての営業力を底上げすることも重要です。ここでは、管理職の方向けに、提案書の品質を標準化するための3つのステップを紹介します。
多くの企業では、労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査でも指摘されているように、「指導する人材の不足」や「育成時間の不足」が課題となっています。仕組みによって品質を担保することは、これらの課題解決にも繋がります。
1. チーム共通の「勝ちパターン」をテンプレート化する
まずは、チーム内で過去に受注に繋がった優れた提案書(成功事例)をいくつか集め、その共通点や「勝ちパターン」を分析します。そして、その要素を盛り込んだチーム共通の基本テンプレートを作成しましょう。
これにより、経験の浅いメンバーでも一定水準以上の提案書を作成できるようになり、チーム全体の品質の底上げが図れます。情報処理推進機構(IPA)の調査でも、多くの企業がIT導入を進める上で「参考にできる事例やテンプレートが不足している」ことを課題として挙げており、テンプレート化は非常に有効な手段です。
2. レビューの観点を言語化し、フィードバックの質を高める
部下の提案書をレビューする際に、「なんとなく分かりにくい」といった感覚的なフィードバックに終始していませんか。これでは部下は何を改善すれば良いのか分からず、成長に繋がりません。
具体的なレビュー観点をチェックリストとして言語化しましょう。客観的な基準に基づいてフィードバックを行うことで、指導の質が向上し、部下の育成も効率化します。
3. 成功事例やナレッジを共有する仕組みを作る
優れた提案書や、顧客から良い反応を得られたフレーズ、分かりやすい図解の仕方など、個人の持つナレッジをチーム全体で共有する仕組みを作りましょう。
定期的な勉強会の開催や、チャットツールでの情報共有など、方法は様々です。成功事例だけでなく、「こういった提案は響かなかった」という失敗事例の共有も、チーム全体の学びを深めます。属人化を防ぎ、組織の集合知としてナレッジを蓄積していく文化を醸成することが、継続的な成長の鍵となります。
まとめ
本記事では、受注率を上げる営業提案書の作り方について、基本構成から書き方のコツ、チームでの品質標準化まで幅広く解説しました。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
- 営業提案書の主役は「製品」ではなく「顧客の課題解決」である。
- まずは『課題提起 → 解決策 → 導入効果 → 実行計画 → 費用』という基本の型に沿って作成する。
- 「相手目線」「PREP法」「データ」「ストーリー」「デザイン」の5つのポイントで質を高める。
- よくある失敗例を反面教師とし、顧客に寄り添った提案を心がける。
- 組織として、テンプレート化やナレッジ共有を進め、チーム全体の営業力を底上げする。
良い提案書は、単なる書類ではなく、顧客との対話を深め、信頼関係を築くための強力なコミュニケーションツールです。まずはテンプレートを活用し、今回ご紹介したポイントを意識しながら、一度ご自身の提案書を作成してみてはいかがでしょうか。その一歩が、あなたの営業成果を大きく変えるきっかけになるはずです。